第2章 テレマティクスの幕開け
G-BOOK開発の舞台裏

「いつでもどこでもつながる」「便利で楽しい情報コンテンツ」「ボタンタッチで誰でも簡単に使える」「車載機(ナビ)だけでなく、パソコンや携帯電話、PDAなど車に乗っていないときでもシームレスに使える」…。最新の通信技術とカーマルチメディア技術が高次元で融合して、これまでにないまったく新しいクルマの価値を生みだすG-BOOK。この次世代テレマティクスを実現するためには、G-BOOKセンターの開発やアプリの開発など技術的な挑戦はもちろん、コンテンツ提供会社の開拓、導入支援など、さまざまな新しい挑戦が必要だった。本項ではこうしたG-BOOK開発の舞台裏に迫る。
大切なのは同じ釡の“パン”を食い、苦楽を共にすること
DCM標準搭載に加えて、WiLL CYPHAに搭載されたG-BOOKが画期的だったのは、対応ナビのプログラムが特別なOSではなく、Windowsで開発され、動いていたということだ。正確には「Windows CE for Automotive。」マイクロソフトが開発した、カーナビゲーションシステムおよび車載機器用のオペレーティングシステムである。これにより、プラットフォームを共通化し、機器メーカーの開発の負担とコストが低減された。
G-BOOKのUI(ユーザーインターフェース)はインターネットの技術をうまく活用したビューワーだった。パソコンの画面上に車載機(ナビ)と同じ画面が表示できたので、車載機(ナビ)が手元になくてもパソコン上で開発や検証ができた。その結果、開発のオープン化を実現。さまざまなコンテンツ提供企業がG-BOOKという共通基盤(プラットフォーム)に容易に参画できた。コンテンツやサービスを後から追加できる拡張性があったのだ。いまのスマートフォンOSなどで多く採用されているオープンプラットフォームの概念を2002年に実現してしまっているのだ。つまり、G-BOOKは生まれながらにして、いまでいうところの「モビリティ・サービス・プラットフォーム」だったのである。その証拠に、WiLL CYPHAの立ち上げ時点で、コンテンツ提供会社は40社以上。業種も保険会社、旅行会社、ゲーム会社、出版社、警備会社、新聞社など多種多様な会社がG-BOOKのプラットフォームに参画していた。
こんなふうに説明すると「なんだ、そんなことか!さぞや簡単に開発ができたに違いない」と思われるかもしれない。しかし、これらはすべて新しい挑戦であった。誰もやったことがないことをやるわけだから、当然、さまざまな困難にぶち当たる。実際、G-BOOKの車載機(ナビ)の開発はかなり苦労した。
この困難を打開するため、当時、横浜にあったナビメーカーの工場の中に大部屋が作られ、車載機(ナビ)開発を担当するトヨタの第一電子技術部の特命チームのメンバーやOSを提供するマイクロソフトのエンジニア、さらには関連ベンダーなどからすべての関係者が一堂に会し、月曜日から金曜日まで、膝を突き合わせて開発にあたった。
大部屋の壁面には、大小さまざまなプロジェクトのスケジュール表や体制表はもちろん、課題管理表がびっしりと貼られ、前線基地さながらの様相。
「なんでこのプログラムのエラーが計画の2日たっても消えないんだ!」
「いますぐ設計書とパソコンもって、俺の机の隣に来い!」
「いまから車載機開発の現場行くから君と君は一緒に行くぞ!」
そんな怒号のような声がそこら中で聞こえる中、多くのメンバーが自身のパソコンのキーをひたすら叩きまくりプログラムを書き上げていく。
毎週木曜日と金曜日の2日間はG-BOOKセンター側から藤原靖久、伊藤誠、井谷周一が出張し、車載機(ナビ)側とお互いの進捗状況の確認やさまざまなすり合わせをおこなっていた。
「車載機(ナビ)開発の大部屋には常時、100人以上の人が全国から集まっていました。G-BOOKセンターの開発現場と同じように、ここでも同じ釜の飯を食う仲間たちの絆が出来上がっていました」と、藤原は当時を振り返る。この大部屋では毎日、夕方になると人数分の牛乳とパンが配られた。「同じパンを食う仲間たちでしたね(笑)」。藤原は夕方のパンがいつも楽しみだった。パンを口にするたびに、壁面のスケジュールの進捗遅れは改善し、記載されている課題の数がどんどん減っていったからだ。
コンテンツ提供会社の開拓
コンテンツ提供会社の開拓を担当したのは、ジャパン・デジタル・コンテンツ社長の藤井雅俊と伊藤誠である。インパクでも活躍したこのコンビがタッグを組んでコンテンツ提供会社各社を回り、G-BOOKへの参画を呼びかけて回ったのである。「何かトヨタがコンテンツビジネスの分野で面白いことをやるみたいだ」。ジャパン・デジタル・コンテンツや藤井個人の人脈を生かして声をかけると、すぐに150社余りの企業が興味を示してくれた。
しかし、この段階で車載機(ナビ)はまだ開発途中。コンテンツを表示する画面がどんな仕様になるのかさえ、決まっていなかった。当然、どんなクルマに搭載されるのかは社外秘。G-BOOKセンターのプラットフォームの開発なんて始まっていない。つまり、構想しかない。具体的に話せることは何もない。そんな状態だった。そこで、藤井は得意のホワイトボードを使って唾を飛ばしながら熱く壮大な構想を語り、伊藤は自分で想像して「画面はこんな感じになります」という資料を作り、説明した。
当時、藤井は銀髪のロン毛、伊藤は金髪のロン毛。そしていでたちはジーンズにTシャツにジャケットが基本という、この金銀ロン毛コンビがドカドカとコンテンツ提供会社に乗り込み、役員応接室で大いに夢を語り、口説いて回る。相手にしてみれば雲をつかむような話であったが、妙に引き込まれた。そんな営業活動を毎日、繰り返した。
コンテンツ提供会社の開発負担を軽減
興味を持ってくれたコンテンツ提供会社がG-BOOKに参画しやすいようにするという配慮から生まれたのが、G-BOOK MLとデバイスゲートウェイである。その開発を推進したのは、GAZOO立ち上げやe-Tower でもその能力を発揮した藤原だ。
「G-BOOK MLとデバイスゲートウェイがあれば、コンテンツ提供会社のコンテンツ作成の負担が軽くなる。そうすれば、より多くの会社に参加してもらうことができる。同時に、車載機(ナビ)だけでなくパソコンや携帯電話、PDA(Personal Digital Assistant)からも利用できるようにして、いつでもどこからでもG-BOOKを使えるようにすればユーザーは便利になる、利用率が上がる、ユーザー数も増える」と考えたのである。
いまであれば、世界中で標準化されているHTML5を使って開発すればさまざまなデバイスがそれを理解するので、わざわざG-BOOK MLとデバイスゲートウェイなんてものを作らなくても、簡単にいろいろな端末で表示させることはできる。しかし、当時はそんなものはない。
なぜなら、同じコンテンツをパソコンや携帯電話などマルチなデバイスで表示させたいというニーズ自体が世の中になかったのだ。「シームレスでマルチデバイス対応」というG-BOOKのコンセプトは、世界的にもユニークだったのだ。だからその開発は技術的にも新しい挑戦だった。その実現に尽力したのが、当時、富士通グループからガズーメディアサービスに常駐していた小川郡治である。「世の中にないから自分たちで作るしかない。G-BOOKのサービス開始も迫っていたので開発期間も短い。正直、これは無理難題でした(笑)」と小川は語る。
特に大変だったのがデバイスゲートウェイの開発である。これは例えるならば自動翻訳機のような働きをするアプリケーションである。G-BOOK MLで書かれたプログラムを車載機(ナビ)やパソコン、携帯電話などのデバイスが正しく理解できるように変換して表示させる役割を担う。一口にパソコンといってもインターネット・エクスプローラやネットスケイプといったブラウザの違いに対応する必要があったし、携帯電話に至ってはメーカーごとにブラウザを独自で作っていたので、その数だけ対応が必要だった。実際に表示させてみて、修正を加える。それを何度も繰り返す。それはとても地道で根気が必要な開発だった。
そして、デバイスゲートウェイは文字通りゲートウェイとしてアプリケーションの入り口で構えていて、すべてのコンテンツはこれを通ってやり取りするので、何かトラブルがあると真っ先に「デバイスゲートウェイに問題があるのではないか?」と疑いがかけられる。責任も重大だった。「それでも、やりきることができたのは、ひとえに、コンテンツ提供会社の負担を減らして、より多くの会社に参画してもらいたい。そして便利に使えて、より多くのユーザーに喜んでもらいたい。そんな一心で頑張りました」と振り返る。
そして、2002年の8月。まずパソコン向けの開発が完了し、e-TOYOTA部の部長による最終確認の日を迎える。当時、e-TOYOTA部にあった役員会議室に関係者がずらりと集まった。その緊張した空気の中、部長の友山が入室してくる。そして、真剣な顔でパソコンに向かい、無言でマウスを動かし始める。テストが始まった。富士通チームの一員だった小川にとって、こんなに近くで友山と接するのは初めてのことだ。第一印象は「怖い人だな」と思った。
ひと通り、確認が終わり、友山が小川の方を見て、ひと言「ありがとう」と告げる。その瞬間、小川の胸にはいろんな想いがこみ上げてきた。「涙こそ流しませんでしたが、あのひと言は嬉しかったですね。そして、こんな熱意を持った人がリーダーなのだと知り、よし、車載機向けの開発も頑張ろうという気持ちになりました」と語る。
さらに、その後を受けて、参画予定の会社を今度はドブ板営業よろしく、G-BOOK MLを使ったコンテンツの作成方法を説明して回ったのが野田俊介である。本来であれば、デモ機を使って実演しながら説明するべきところだが、車載機(ナビ)は開発途中だった。そこで、野田はG-BOOK MLで作成したコンテンツをパソコンのG-BOOKビューワーで表示して確認してもらった。それで画面表示の確認はできるが、G-BOOKがウリにしていた音声読み上げの実演はできなかった。
まだデモ機ができていないことに対して、中には「本当にG-BOOKって立ち上がるの?」と不審がる会社もあった。そこはただ「大丈夫です」というしかなかった。
そして、2002年5月になって、やっと待望のデモ機が野田の手元に届く。しかし、それは堅牢でばかでかく、重かった。「これじゃあ、持ち運びができない」。野田は木製のボードを購入し、そこにデモ機の部品を自ら取り付け、スーツケースに入るサイズに改良した。そして、それを持ってコンテンツ提供会社をひたすら回った。東京にウィークリーマンションを借りて、長期出張し、朝から晩までスーツケースを持って電車で東京の街を徘徊した。1日5社以上訪問することもあった。訪問した会社数は150社を超えた。大きなスーツケースを持って朝の満員電車に乗るのは苦痛だった。
G-BOOK MLの仕様は度々、変更された。同時並行での開発だったので仕方ないとはいえ、変更があるとそれをコンテンツ提供会社に伝え、お詫びして作り直してもらうのも野田の仕事だった。
コミュタロー冤罪事件
走行中のナビの目的地設定ができるコンテンツとして、「コミュタローナビ」というユニークなハンズフリー音声認識システムが試験サービス中として提供されていた。携帯電話を車載機に接続し、車載機からコミュタローを呼び出してハンズフリー電話で会話する。DCMからクルマの位置情報がG-BOOKセンターに送られ、センターのサーバーで音声と位置情報を処理して応答する。いまでいうところのAI機能である。これも新しい挑戦の一つだった。
コミュタローが「用事はなあに?」と聞いてくるので「ナビ設定してー」と応えると、「どこ行くの?」と聞いてくる。そこで目的地の名前や施設名、電話番号などを告げるとコミュタローがナビに目的地を設定してくれるというものだった。
しかし、これがなかなかうまくいかない。自信なさげに「ここでいいの?」と聞いてくるので「違うよ」というと、「ごめんね」と再度、行き先を聞いてくる。これを何度か繰り返すと、急に「また用事があったら呼んでね」と告げて、一方的に通話を切ってしまう。「おいおい!都合が悪くなったら帰っちゃうのかよ!」と突っ込みどころ満載のコンテンツだった。本来ならクレームになりそうなものだが、これが逆に「かわいい」と人気になってしまうのだからおかしなものである。「頑張れ!コミュタロー」とばかりにファンクラブやキャラクターのぬいぐるみまでできてしまった。このキャラクターデザインも伊藤誠が担当した。
一方で「G-BOOKの通信速度が遅いのはコミュタローのせいではないか?」という疑惑がセンター内で持ち上がり、ナビ画面でコミュタローがコミカルなアクションをして和ませてくれるコミュタロー・アクティブモードが一時中止になった。その後、コミュタローの担当者が必死になって調査し、無実を証明。疑いが晴れ、サービスが再開された。これが「コミュタロー冤罪事件」である。「コミュタローナビ」はうまくいかないことが多かったので、試験段階で中止になったが、「なぞなぞ」や「占い」の機能は、「コミュタローと遊ぼう」というコンテンツとして存続。このコミュタローは、いまの「Siri」や「Googleアシスタント」などのAIエージェントの
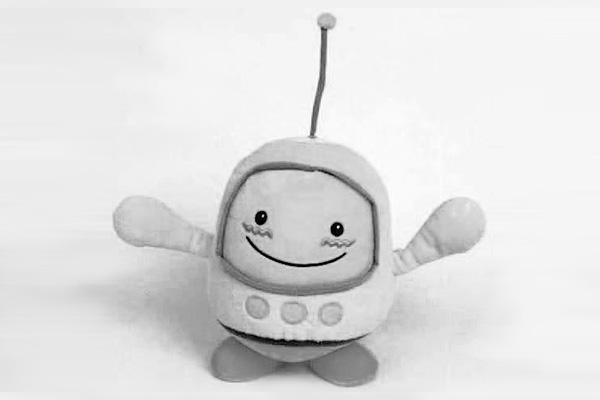
この章の登場人物
-
- 藤井 雅俊(ふじい まさとし)故人
- ジャパン・デジタル・コンテンツ元社長
トヨタコネクティッド元エグゼクティブプロデューサー - トヨタコネクティッドのコンテンツビジネスの水先案内人として、デジタルコンテンツ事業の礎を築いた功労者。G-BOOKでは、伊藤とともに約150社あまりのコンテンツプロバイダーへ営業。これまでのエンタメ業界での深いつながりから、カラオケコンテンツやG-SOUNDなど充実したコンテンツにつながった。トレードマークは、銀髪に黒のジャケット、ブルージーンズ。お客様との打合せにもこのいで立ちで登場し、相手先の経営層を驚かせたが、誰しもがその熱い想いや彼の語る未来に引き込まれ仲間になっていった。クールでスタイリッシュな風貌からは想像できないほどの熱血漢であり、TCの次世代を担う若手マネージャからの信望も厚かった。
-
- 野田 俊介(のだ しゅんすけ)
- トヨタコネクティッド 先行企画部 技術企画室長
- 最初はGAZOOドットコムの携帯電話サイトのコンテンツ提供会社だった日本エンタープライズでGAZOO担当だった。立場を超えた、その歯に衣を着せぬ物言いが友山の目に留まり、「G-BOOKのコンテンツ提供会社への営業担当として是非、手伝って欲しい」と同社に依頼。GMSに出向する。G-BOOKへの愛着は人一倍強く、WiLL CYPHAが発売されると同時に販売店に走り込み、即決で注文書にサインをするほど。WiLL CYPHAの全色を揃えて実施した浜名湖から豊田佐吉記念館へのドライブツアーに彼女同伴(現在の奥様)で参加した。その後、GMSに入社。G-BOOK ALPHA、G-BOOK mx、T-Connectと手掛けたサービスはすべて即購入。こうと決めたら他の誘惑に乗らない、首尾貫徹の姿勢は周りから野武士とも呼ばれる。
-
- 小川 郡治(おがわ ぐんじ)
- トヨタコネクティッド コーポレートIT部 主査
- 2002年に富士通の子会社からプロジェクトに合流した、情に厚い元マイルドヤンキー。当時は多数の高級時計を所持するだけでなく高級スーツを着こなし、夜な夜な街に繰り出す一面も。藤原や井谷と共にG-BOOK MLやデバイスゲートウェイを立ち上げに尽力。担当業務はスウィーパー的なポジションで、日々発生する課題を取り纏め、1件づつ現場で潰す、地味だが重要な業務を担っていた。当時の役員の人間力に惹かれGMSへの入社を決め、コールセンター長を経て、現在はトヨタコネクティッドのセキュリティ部門のヘッドとなりその手腕を振るう。


